別記事「セワシは学年誌200周年に立ち会ったのか?」を書く上で、小学館の学年誌「小学一年生~六年生」の正確な発行年月が必要でした。しかし公式HPでも年レベルしか載っていなく、セワシの記事に使うために必要な年度情報(4月~12月号なのか、1~3月号なのか)が得られませんでした。wikiの情報も年しか無いし、ネット上の他情報も孫引き的に情報がズレて紹介されている例もあったので自力で信頼できる情報を調べました。そしたらまるで推理モノみたいに年月が推定できたので思わずうれしくなりその推論ロジック、過程の記録を残しておきたいと思います。
結論
先に調査結果まとめです。一、二、五、六年は確定的なソースがあったので簡単でした。
しかし一番欲しい四年生の確定的な情報がなく苦労しました。最終的には推定できましたが推測である事にご注意ください。
| 雑誌名 | 創刊号 | 年度 | 確信度、ソース |
|---|---|---|---|
| 小学一年生 | 1925年4月号(3月発売) | 1925年度 | 小学館公式HPより。 |
| 小学二年生 | 1925年4月号(3月発売) | 1925年度 | 小学館公式HPより。 |
| 小学三年生 | 1925年1月号(12月発売) | 1924年度 | 小学館HP、国会図書館HP、昭和館、現存する雑誌より推測。 |
| 小学四年生 | 1924年1月号(12月発売) | 1923年度 | 小学館HP、国会図書館HP、現存する雑誌から推測 |
| 小学五年生 | 1922年10月号 | 1922年度 | NEWSポストセブン記事より。 |
| 小学六年生 | 1922年10月号 | 1922年度 | NEWSポストセブン記事より。 |
まずは確実な情報の紹介
いくつかの正確なメディアで紹介された情報がありました。これでだいたい特定できます。
ついに1925年3月、『セウガク二年生』と『セウガク一年生』が発行され、全学年の学習雑誌が揃いました。(中略)
引用元:小学一年生HP 1925(大正14)年〜1938(昭和13)年: 『セウガク一年生』創成期
この年の3月に『セウガク二年生』4月号、『セウガク一年生』4月号が創刊され、学習雑誌の学年はすべて揃いました。
『小學五年生』大正11(1922)年10月号(創刊号)全学年の中で、『小學五年生』から学年誌は始まった(『小學六年生』も同時創刊』)
引用元:NEWSポストセブン 画家・玉井力三の世界 学年誌の表紙画の進化と輝いていた昭和の時代に壇蜜も感嘆
1923年…『小学四年生』創刊
引用元:小学館HP「沿革・歴史」
1924年…『せうがく三年生』創刊
不足しているのは小三、小四の月情報だけです。これらは直接的な公式情報が見つからなかったので、周辺情報から推測をしていく事にしました。
小学三四年生の創刊号は何年何月か。
当時のカウント方式から探る。
オークション等で散見する初期の学年誌の表紙から読み取ると「2025年4月号」のような年月表記ではなく
「大正十五年 六月」、「第三巻」、「第十號」
のような表記になっています。◯巻が創刊年からの経過年度数、◯號はその巻での発行数のようです。なので、創刊号が見つからなくても逆算的に創刊年度までは推定する事はできそうです。(號は創刊号が4月始まりとは限らないので月までは求められない)
小学三年生:1925年1月号(1924年12月創刊)トリッキーに絞り込めた!
できるだけ信頼度の高い情報を使います。まずは国会図書館に載る情報。また古本サイトなどに掲載されている実物写真から読み取れる情報に誤記は無いだろうという考えで進めます。
国会図書館のHPだと所蔵されている最古の情報が「5巻10号 (昭和4年1月)」なので逆算すると創刊は1924年度となります。また古本販売で実物の表紙が読み取れる例もあり「第二巻十二號(大正15年三月)」とあるのでこちらとも計算結果は合います。ここから、1924年度である事は確定的だと思います。
さらに絞り込みます。
昭和館デジタルアーカイブHPには創刊が1924年12月という具体的な月が載っていたのでこれを信じてもいいのですが、ただ号数を指しているのか発行月を指しているのかまではわかりません。ダブルチェックしたいなと思っていた所、トリッキーな絞り込みができました。
まず小学館HPの沿革・歴史には1924年創刊とあります。一方、国会図書館では初出版年1925年とありズレているようにも見えますが、これが逆に使える情報になりました。国会図書館の出版年表記は実際の発売日ではなく、雑誌表記上の年月(◯年◯月号)に合わせるルールのようです。1学年誌は書いてある号数より1ヶ月前に発売するというのが基本形で、当時の小学一年生も4月号を3月に発行したとあるので大正時代でもこの方式だったと見て良さそうです。
ここから、創刊の号数的には1925年だが発売的には1924年という状況は「1925年1月号を1924年12月に発行」パターンしかないため、2つの情報からこれを信じて良さそうだという結論に至りました。
なんか推理モノみたいでうれしい!
小学四年生:同じ考えをすれば1924年1月号(1923年12月創刊)
小三と同じ推定ロジックを使います。
国会図書館のHPで小学四年生を調べると所蔵されている最古の情報は「3巻5号 (大正14年8月)」なので逆算すると1巻は1923年度。またこの古本サイト掲載の小学四年生はかなり古い実物の表紙がはっきり読み取れて「一月、第二巻、第十號、大正十四年(=1925年)」とあります。これも逆算すると創刊は1923年度なので間違いなさそうです。
そして国会図書館HPには初出版年が1924年、小学館 公式HPの沿革・歴史には1923年創刊とあります。なので小三と同じ推論ロジックを適用するとこれも1924年1月号(1923年12月発行)と考えて良さそうです。ついに欲しい情報にたどり着いた!
まとめ
という事で、絶対正しい情報!とは言えない部分もあるのですが、各種推論からよほど間違いないんじゃないかなあと思えるレベルには絞り込んだつもりです。少なくとも年度についてはほぼ確定的だと思うので、セワシの計算には使えるようになりました。
推定根拠やソースも載せていますので、もし間違いや別の推論あれば指摘お待ちしております。また直接的な情報をご存知の方がいましたらでしたら教えてください!
脚注
- 例えばドラえもんが連載開始した小学四年生1970年1月号(実際の発売は1969年12月)の情報ページを調べると、出版年1970年1月と書かれているので実際の発売年月ではなく雑誌の表記年月で載せるというルールのようです。 ↩︎
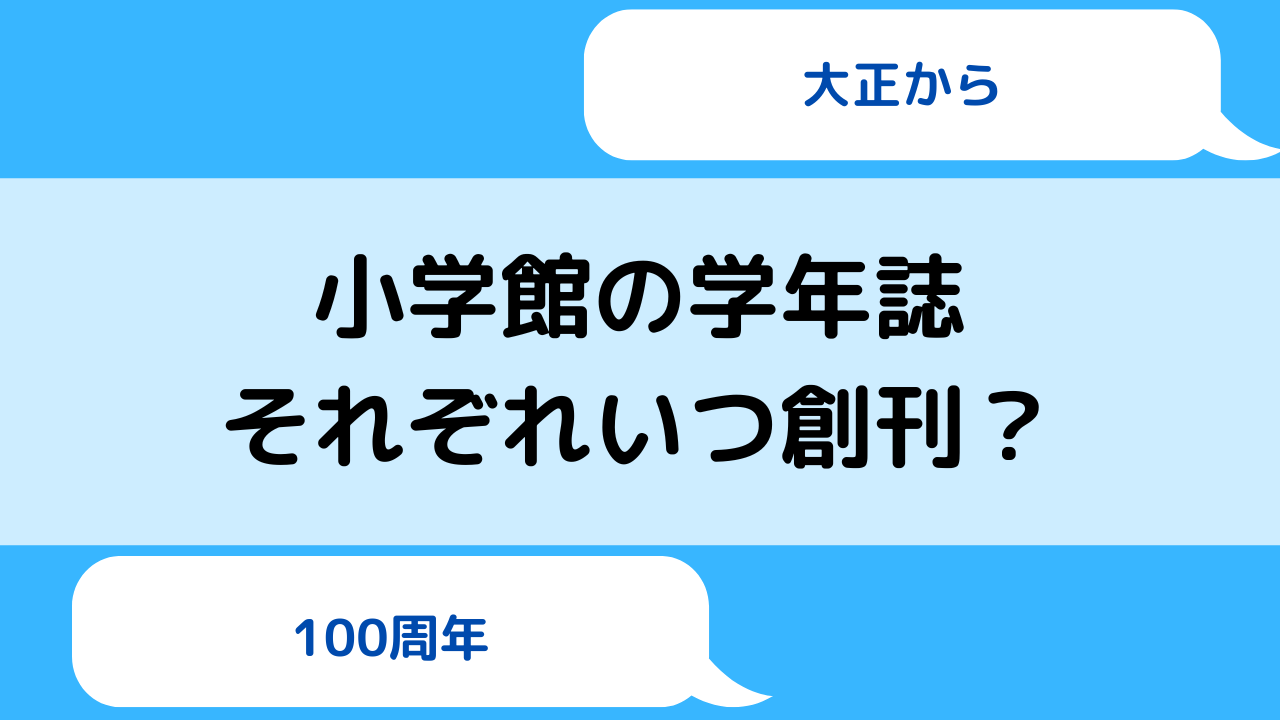
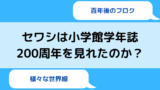

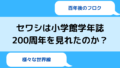
コメント